「ローテーション」の基本
- 勇樹 坂本
- 2017年9月17日
- 読了時間: 3分
さあ、4つめのトピックです。話題は色々あるのですが、バレーボール観戦において知っていたらより深く楽しめるものを、優先的にお話ししたいと思います。今回のトピックは、「ローテーション (以下ローテ)」についてです。実は7月から記事を書いていましたが、落としどころがわからず2か月放置してしまいました。ということで、非常に簡単な話しかしないので気楽に読んでもらったら、と思います。

上図のように、バレーにおいて6つの区画が存在し、これをもとに時計回りにローテしていきます (この区画は形式的なもので、コート上に線があって6つに分けられているわけではありません)。サーブを打つのは右後ろの選手となっており、この図で言うと1番の選手となります。
では、いつローテするのかというと、相手から自分にサーブ権が移動したとき、となります。
となると、サーブ権とはなんぞや?という疑問が浮かびますね。
サーブ権とは、サーブを打つ権利であり、直前に得点をしたチームに与えられるもの、です。
これだけでは非常に分かりにくいので、上図を用いて具体例で考えてみましょう。
1番の選手のサーブで試合が始まりました。なんといきなりサービスエース!1番の選手は大喜びです!
・・・さてこの場合どうでしょうか?
直前に得点したチームは・・・自チームですね。
では、相手から自分にサーブ権が移動しましたか?
自チームのサーブから始まっており、サーブ権の移動はありませんね。
この場合ローテは起こらず、引き続き1番のサーブとなる訳です。
次に1番がサーブミスをしたとします。相手チームに得点が入り、相手にサーブ権が移りますね。そう、ここで相手チームはローテするのです。さらに、ここで相手がサーブミスをしたとします。自チームに得点が入り、ローテが起こりますね。時計回りにローテするので、次のサーブは2番になります。つまり、サーブ順は1-2-3-4-5-6-1-2・・・となることがわかりますね。
次に、ローテの意味について軽く考えます。バレーボールにおいては、前衛 (図の4,3,2)と、後衛 (図の1,5,6)というくくりが存在します。前衛と後衛の違いは何なのか??決定的な違いは、攻撃参加権です。前衛プレーヤーはアタックを打つ上で制限というものはありません。しかし、後衛プレーヤーは、アタックライン (図の4,3,2の下にある濃い線、ネットから3m離れている)より後ろからしか攻撃ができないのです。ということは、攻撃力が高い人を出来る限り前衛に長くいさせたい、と考えるのは当然のことですよね。
また、ローテは、前衛プレーヤーにとっては「後衛に近づくいやなもの」、逆に後衛プレーヤーにとっては「前衛に近づくありがたいもの」、であることがわかりますか?上図の状態で1個ローテすると、2番は後衛に下がりますし、3番もあとひとつで後衛、という位置に来ます。逆に5番は前衛に上がりますし、6番はあとひとつで前衛なわけです。
つまり、エースが前衛の時は、出来る限りローテをさせないようにして、逆に後衛の時は、積極的にローテを回してエースをいち早く前衛に上げるようにするのです。エースが後衛の時にいかに耐え忍ぶか、逆にエースが前衛の時にいかにしてたくさん点を取るか、どちらも重要な課題であり、そのチームの戦略の一端を垣間見ることができます。
いかがでしたか??バレーボールにおける、ローテーションのルールと基本的な考え方についてお話ししました。前衛、後衛、そしてローテーションの関係について、複合的な話をいずれしたいと考えていますが、今回は軽い話で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ハマー




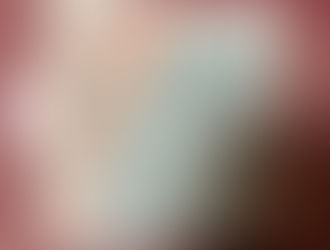












コメント